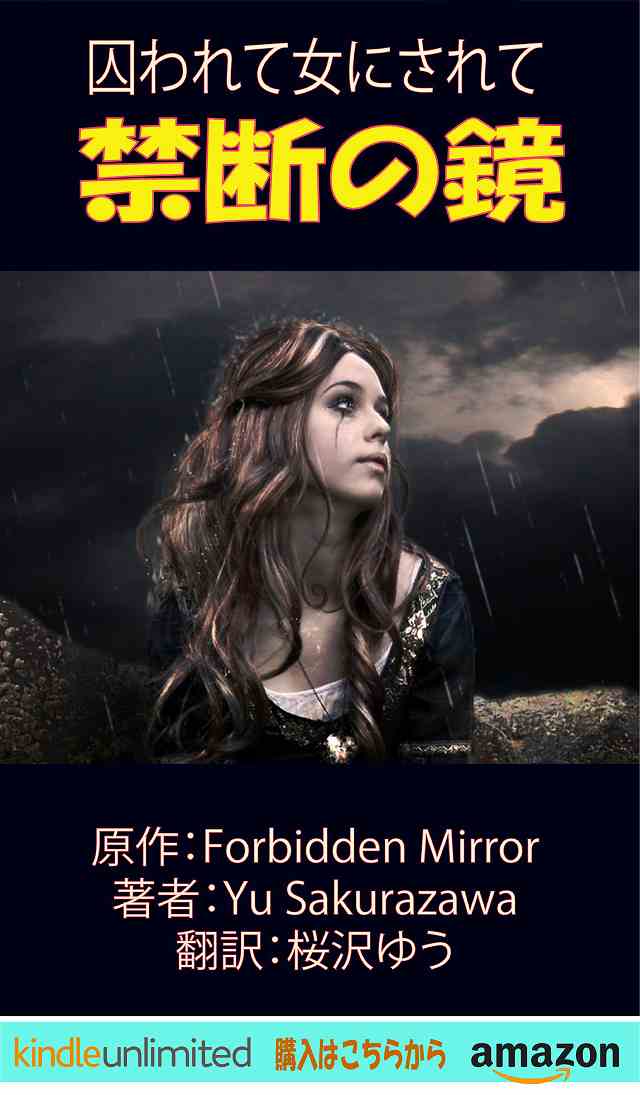
禁断の鏡
囚われて女にされて
第一章 鏡の預言
夕食の後で父に呼ばれた。
「アーロン、ちょっと話があるんだが」
普段とは全然違う口調だったので僕は身構えた。叱られるのかもしれない。きっと悪い話だと直感した。
「シャキーラは覚えているな?」
「シャキーラって、一昨日のパーティーに来ていたお姉ちゃんのこと?」
「そうだ。実はシャキーラと結婚することになった」
「誰が?」
「お父さんがだ」
「ええーっ!」
僕は絶句した。
一昨日は父の誕生日で、例年通り大勢の客を家に招いてパーティーを開いた。父は大会社のオーナー社長で政財界にも顔が広いが、誕生パーティーに呼ぶのはごく親しい人たちだけであり、家族を含めて二、三十人ほどだ。招待客の中に一人だけ僕とさほど年齢が離れていない人が混じっていた。それがシャキーラだった。
クリーム色のレースのドレスを着たきれいな女の子が来たのを見て、僕より少し年上かな、と気になっていた。父と彼女がワイングラスを持って談笑し始めたので、十八歳以上だと分かった。その時、父から呼ばれて彼女に紹介され、立ち話をした。
パーティーの時に僕が父の友人に紹介されて型通りの立ち話をするのはよくあることで、彼女もその一人だった。十二歳の僕より少し年上の少女ではなく、お酒も飲める大人だと分かったので、僕は彼女に興味を失い、彼女のことは気にしていなかった。
「シャキーラは見かけほどは若くはないんだよ。アーロンの新しいお母さんになる人だから、暖かく迎え入れてくれ」
僕は「分かった」と返事して自分の部屋に行き、ベッドに仰向けになった。
ショックだった。
母が亡くなってもうすぐ一年になる。父が葬儀の日に「私が本気で愛した唯一人の女性だった」と言ったのが今でも耳に残っている。たった一年で母の事を忘れて、自分の娘のような年齢の女性を好きになるとは……。
僕の母、ブリオニーはこのウィンダーミアで最も美しい女性と言われていた。
ストロベリー・ブロンドの長い髪は風に揺れるアザミのように鮮やかだった。僕はいつも母と一緒だった。母と二人で森に行ってキノコ採りをしたり、一日かけて山や湖を回った思い出は僕の宝物だ。僕は母には何でも話せたし、母も父には言えないことまで僕に話した。母と僕は毎日楽しく笑って時を過ごした。
その笑いがある日突然途絶えた。乗馬をしていた母が馬から落ちて首の骨を折ったのだ。溌溂としていたウィンダーミアが朦々となり小鳥たちも歌わなくなった。父は生きた亡霊となって殻に閉じこもった。
明るい父に戻ったのはごく最近だった。シャキーラと出会ったことで父は自分を取り戻したのだろう。後で聞いたところによると父はギリシャに出張した際にシャキーラと出会い、シャキーラのエキゾチックな美しさに魅了された。シャキーラというのはフルネームであり、ミドル・ネームも姓も無いとのことだった。等身大の彫刻かと見紛う完璧な肉体、褐色の顔とつりあがった目。シャキーラは生粋のギリシャ人ではなく先祖は外国からの移民だという噂もあった。それがトルコなのか、中東なのか、北アフリカなのかは誰も知らない。
結婚式の日、シャキーラがベージュのウェッディングドレスを着て穢れの無い白いバラのブーケを手にして立っている姿を見て、父の気持ちが分かる気がした。彼女が放つ捉えどころのない香り、彼女の動きのしなやかな気品、そしてオオカミを連想させる微笑みの不思議な魅力が人々を虜にした。
僕にとって、シャキーラは世間でいう継母の典型とは程遠かった。シャキーラは僕に対してとても親切で、どこにでも一緒に連れて行ってくれた。友達の家でのカクテルパーティーや美容室にも僕を連れて行くし、ロンドンのグローブ・シアターにも一緒にシェークスピアを見に行った。
「僕、邪魔になるのはいやだから、無理してどこにでも連れて行ってくれなくてもいいよ」
と僕は十二歳の少年らしい遠慮をしたことがある。
シャキーラは形の良い手で僕の頬を包んで答えた。
「アーロンは私の弟みたいなものだから、邪魔だなんて思ったことはないわ。一緒に来てくれると心強いのよ」
シャキーラのフランス語訛りが素敵だった。僕は、この上なく美しいエキゾティックなシャキーラの虜になった。もしシャキーラが義理の母親でなかったら、間違いなく恋をしていただろうと思う。
僕は広大な屋敷の敷地を、亡くなった母と一緒に散歩したものだが、シャキーラとは仲良しの姉弟のように走り回った。敷地の中央にある屋敷は灰色の三角屋根がある大きな白い建物だった。屋敷の前には大きな庭があって、季節にはバラやツツジが咲き誇った。
屋敷の横手には馬小屋があり、父の自慢のサラブレッドが居た。馬小屋の裏には、父から決して近づかないようにと言われていた石造りの倉庫があった。その倉庫は何百年も前に建てられたものらしく、ずっと鍵がかかったままだと聞いていた。
ある晴れた日曜日の昼下がり、父はフランスに行って不在だったが、シャキーラから一緒に倉庫を探検しようと誘われた。
「ダメだよ。絶対に近づかないようにとお父さんから言われているもの。シャキーラもそう言われただろう?」
「どうして入っちゃダメなのかなあ?」
「そりゃあ、お化けが出るとか、悪霊に取りつかれるとか……」
「アーロンって子供ね。すごい財宝とか、もしかして死体が隠されていたらどうする?」
僕は怖くなった。背筋に寒気が走るのを感じた。
「私がついているから大丈夫よ。さあ、冒険に行くわよ」
シャキーラからそこまで言われて断れず、渋々ついて行った。
倉庫の鍵は冷蔵庫の上にあった。馬小屋の横を通ると、石造りの倉庫が僕たち二人を手招きするかのように立っていた。二人は磁石で引き寄せられるように倉庫のドアまで行き、鍵を開けて中に入った。手をつないで足を踏み入れる。シャキーラの手は汗で湿っていた。シャキーラが小鹿のような黒い目で僕をちらりと見た時、好奇心と不安が入り混じった輝きが見えた。
僕はまだ髭が生えていない鼻の下に汗の粒を感じた。シャキーラと僕は父の言いつけを無視することで、大きな間違いを犯そうとしているのかもしれない。しかし、倉庫の中に足を踏み入れてしまった今となってはもう遅い。
建物の中に入ると、外の世界とは空気がガラッと変化したのが感じられた。それは何とも言えない奇妙な変化だった。地球上に存在する父の屋敷の敷地の中にいるのに、他の惑星にワープしたかのような違和感を感じた。僕の周囲の空気は濃すぎてネバネバしている。飛行機に乗っていて機内の気圧が急に変化した時のような感じだ。倉庫の中には不思議な静寂があって、夢の中を歩いているような気がした。
シャキーラも同じことを感じているのが見て取れた。シャキーラは握っていた僕の手を放し、この世のものではないものを見るような目をしてふらふらと歩いている。彼女は倉庫の中に置かれている虫食いだらけ巨大なカーテン、数えきれないほどの陶磁器などを片っ端から手で触れながら歩き回り、僕はその後について回った。
僕たちはお互いの息吹を強く意識していたが殆どトランス状態だったかもしれない。
シャキーラは高い位置にある閉じた窓の隙間に見える光に引き寄せられるようにふらふらと歩いて行き、その下のキラリと輝くものに目を止めた。二人で近づいて見ると、それは造り付けの鏡だった。
周囲を貝殻で飾られた円形の鏡で、見たことが無いほど豪華で美しかった。不思議なことに、鏡には一点の曇りもなかった。
シャキーラは夢見心地のような顔つきで鏡の前に立った。僕がすぐ斜め後ろから覗くと、黒を基調にメイクした目、細い鼻筋とハートの形の口をした、形の良いシャキーラの顔が映っていた。東洋風の黒い髪が彼女の美しさを際立たせている。
シャキーラは自分のあまりの美しさにポカンと口を開けて鏡を見ていたが、彼女の声とは思えない歪んだ声で鏡に向かって言った。
「鏡よ鏡、鏡さん。イングランドで一番美しいのは誰?」
倉庫の中がシーンと静まり返った。ピン一本を落としても聞こえる程の静けさだった。その時、信じられないことが起きた。ほんの僅かだが、鏡の表面がピクッと浮き出るように動いた。それは地震で地球の岩盤が上に押し出されるようなイメージで、その鏡が誰かの顔のようにぼんやりと見えた。その顔から答えが返って来た。
「生きている人の中で最も美しいのはシャキーラだ。お前の美しさと優雅さには誰も敵わない」
シャキーラはブルブルと震えながら後ずさりした。僕も同じように後ずさりした。僕たちは風に揺れる葉っぱのように震えながら顔を見合わせた。
あれは年寄りの男性の声だった。ある考えが僕の頭をよぎった。こんなことが起きるはずがない。誰かが僕たちを引っかけようとしているのだ。シャキーラの小鹿のような目を覗き込むと、同じ疑いを抱いていることが分かった。
僕たちは何も言わずにドアの方へと駆けて行ってパッとドアを開けた。ドアの外には誰も居なかった。はるか遠くまで見渡す限り、人っ子一人見当たらなかった。あれは鏡の声だったのだ。
「夢を見てたんじゃないことを確かめるためにもう一度やってみましょう」
とシャキーラが言って、尻込みしている僕の手を引っ張って倉庫の中に入って行った。彼女は鏡の前に立って、先ほどと同じ質問をしっかりとした声で繰り返した。
再び誰かの顔のようになった鏡が、先ほどに劣らないほどはっきりと同じ答えを返した。
僕たちは畏れおののきながら視線を交わした。二人が見聞きしたことが幻想でなかったのは確かだった。
***
その夜、僕は寝付けなかった。昼間に起きた事を何度も思い返し、倉庫の中のこの世のものではない静けさ、空気のどんよりとした重さ、それに何よりもあの鏡が顔のようになったのを見た時の怖さを改めて感じた。
昼間にシャキーラと僕に父の言いつけを破らせたのと同じ衝動が、もう一度あの倉庫に行くようにと僕を駆り立てた。もし父に知られたら叱られる。僕は懐中電灯を手に、パジャマ姿のまま寝室を出て、音を立てないように階段を下りた。冷蔵庫の上の鍵を取り、そっとドアを開けて玄関を出た。誰にも気づかれなかったようだ。
外に出るとひんやりとした夜の空気が頬を洗った。満月の夜だったが、懐中電灯で足元を照らしながら歩いた。
馬小屋の横を通って古い石造りの倉庫に着いた。入り口の鍵を開けて中に入った。昼間来た時に濃すぎてネバネバしていると感じた空気は、今はもうドロドロになっている。倉庫の中は昼間よりも更に静かで、不気味なほどの静寂に覆われていた。右の奥の窓の下に鏡が見えた。僕は夢遊病者のような足取りで鏡に近づき、畏敬と恐怖の混じった気持ちで鏡の前に立った。
僕の顔が映り、アーモンドの形の大きな目と青みがかったグリーンの瞳、すっきりとした鼻、形の良い唇と桃のような顎が鏡の中に見える。母譲りのストロベリー・ブロンドの髪が懐中電灯の光を受けて輝いている。
「鏡よ鏡、鏡さん。過去と現在と未来において、イングランドで一番美しいのは誰ですか?」
と僕は声を震わせながら恐る恐る質問した。
鏡の表面がピクッと浮き出るように動いて、顔のようなものがぼんやりと浮かび上がった。今日の昼に聞いたのと同じ年寄りの男性の声で答えが返ってきた。
「お前のお母さんのブリオニーが最も美しかったが、ブリオニが死んでからはシャキーラが一番になった。そして、将来はアーロン、お前がイングランドで一番美しい人になるだろう」
続きを読みたい方はこちらをクリック!