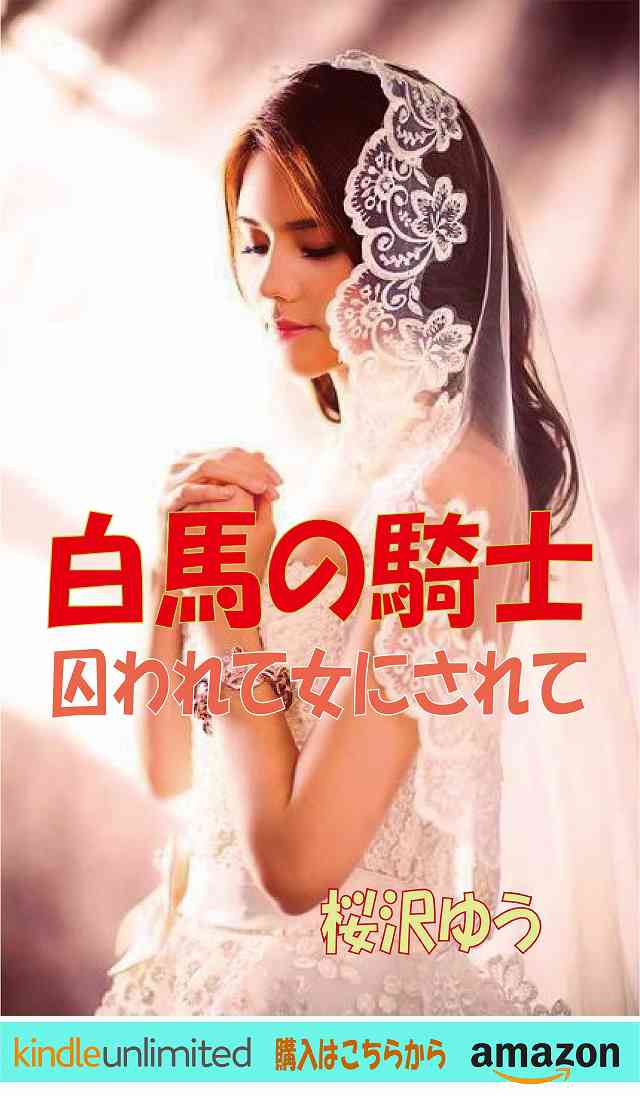
白馬の騎士
囚われて女にされて
第一章 絶体絶命の危機
「に、に、に、にじゅうごまんえん!!」
勘定書きを見て酔いが一気に醒めた。
「冗談はやめてください。心臓に悪いですよ」
どう反応すればいいのか判断がつかず、とりあえずそう言ったが、店長らしい男性の目は笑っていなかった。
「お客さん、楽しんだ分は払ってもらわないと」
「一時間四千円ぽっきりと言ってたじゃないですか!」
「誰がそんなことを言ったの?」
「階段の下で立っていたこの店の若い男の人ですよ。『税込みですか?』と聞いたら『税サ込み込みです』と言うから、『本当に税サ込みで四千円ぽっきりなんですね?』とくれぐれも念を押した上でこの店に入ったんですから!」
「ハア? うちの店は客引きなんてしていないよ。ヨソの店の店員に言われたことをお客さんが勝手に勘違いしたんじゃないの?」
「絶対にこの店の人ですよ。二階の入り口まで案内してくれて、そこのドアを開けてくれましたから」
「お客さん、妙な言いがかりをつけられては困るな。『墨田区客引き行為等の防止に関する条例』が去年の暮れに改正になって、客引き行為をすること自体が違法になったんだよ。うちの店が違法行為をしていると言いがかりをつけるからにはそれなりの覚悟があるんだろうな?」
――ひっかかってしまった……。
ぼったくりバーのことはテレビで見て知っていたし、以前歌舞伎町を通った時に客引きにはついていくなという警告放送を聞いたこともあった。上司に連れられてこの辺りの飲み屋に来たことはあったが、元々アルコールは弱い方だし、一人でバーに入るのは今日が初めてだった。
こんなところに来たくて来たわけではない。ヤケ酒を飲みたい気持ちで歩いていたら四千円ぽっきりで女の子と話ができると言われて、ついふらふらっと入っただけだ。
四月に入社したばかりだが、製造部門での検査データ書き換えが明るみに出て、会社はあっという間に倒産の危機に直面する状況になった。中高年を対象とした肩たたきが始まったことは社内のうわさで聞いていたが、金曜日に課長から会議室に呼び出されて
「今のキミならどこにでも再就職できるよ」
と言われた。
「うちの部は、あと一人退職者が出れば当面のノルマが達成できるんだ。といっても、キミに退職を迫っているのではないから誤解しないでくれよ」
と言われて会議室を出たが、自分は期待されていない人材であると思い知らされた。三昼夜悩んだ挙句、今日退職届を出したのだ。
「今、いくら持っているの?」
僕は財布を出して中味を示した。
「一万四千円です」
「なんだ、クレジットカードを持ってるんじゃないか。限度額はいくら?」
「二十万円ですけど、新しいスマホを買うのに五万六千円使ったばかりです」
「それなら十四万円引き落とさせてもらおうか」
店長は僕の財布からクレジットカードを抜きだしてカードリーダーに差し込み、金額を打ち込んで僕に暗証番号のインプットを迫った。
銀行預金の残高と、もうすぐ振り込まれる予定の給与の日割り分にわずかな退職金を合わせると、クレジットカードで二十万円の引き落としがあっても大丈夫だ。でも、来月のアパートの家賃の引き落としの時点でピンチになる。
相手は大男であり腕力で勝ち目はない。あの客引きの男がこの店の従業員でなかったと言われれば、僕の方に歩は無さそうだ。
「お金を払えないんだったら、警察を呼んで、親御さんに払ってもらうことになるよ」
「いえ、それは困ります」
僕はとっさに暗証番号を入力してしまったが、すぐにそれを後悔した。高校生でもないのに警察と親を呼ぶと脅されてビビるとはバカだった。警察を呼びたいのは僕の方だ。
数秒後に店長は笑みを浮かべて端末からカードを抜き取った。僕はカードを取り戻そうと手を出したが、店長は
「そうはいかないよ」
と言ってカードを引っ込めた。
「本当に限度額は二十万円なの? 普通は三十万円だろう?」
店長はクレジットカードを端末に差し直し、十万円と入力した。僕がさきほど打ち込んだ暗証番号を盗み見して覚えていたらしく、店長は勝手に四桁の番号を入力した。
「蹴られたか。限度額は本当に二十万ぽっきりだったんだな」
店長はクレジットカードを僕の財布に戻し、キャッシュカードを取り出した。
「合計で十五万四千円を払ってもらったから、残高は九万六千円だな。さあ、これからATMに行って引き出してもらおう」
「勘弁してくださいよ。預金残高は六万円前後しかないですし、もし引き出したら、クレジットカードが引き落としできなくなります」
「それはお客さんとクレジットカード会社の間の問題であって、うちの店には関係ないんだよ」
と言って、店長は僕の財布を自分のポケットに入れた。
相手は何枚も上手だと痛感した。
「そのスマホ、買ったばかりだと言ったね? ちょっと見せてもらおうか」
店長はクレジットカードと同じ暗証番号を使ってスマホを開いた。別の番号にすればよかったと後悔したが後の祭りだった。
「最新鋭のアンドロイドか。この機種ならヤフオクで四万円以上で売れそうだな」
「待ってください。スマホを取られたら何もできなくなります!」
「九万六千円をATMで引き出してくれたらその場で返すよ」
僕は手首を強く掴まれて引きずられるようにして店を出た。
カードの引き落としの日に残高が足りなかったら銀行から電話が入るはずだ。もしその時点で返すあてがなかった場合、僕は何と答えればいいんだろうか? スマホが無いと銀行からの電話を受けることさえできない……。僕は極度に混乱していた。
階段を下りたところには、あの客引きの男が立っていた。僕は頭に血がのぼった。
「あの男に四千円ぽっきりと言われたんだ!」
僕は大声で叫んで、その若い男を問い詰めに行こうとしたが、僕の右手をつかんでいる店長の力には敵わなかった。
僕は周囲に聞こえるように大声で叫んだ。
「離せ! あの男はお前の店の客引きだろう! 僕はあいつに四千円ぽっきりと騙されてお前の店に引っ張り込まれたんだ!」
言い終わらないうちに男は右手で僕の顎を掴んで口を塞いだ。僕はとっさに右ひざを男の股間に食らわせた。男が「ううっ」と言って手を離した隙に僕は男を突き飛ばし、走って逃げた。細い道を曲がって十メートルほど進んだところで、追いかけて来た若い男に肩をつかまれて路上に転がされた。
「お前が僕を騙して客引きしたんだ。客引きすること自体が違法だと知らないのか!」
僕は地面に腰を付いたまま、さっき教えられたばかりの条例を持ちだして若い男を罵った。
「騙して客引きしただと? 証拠でもあるのか?」
立ち上がろうとした僕はスネを横から足で払われて地面に倒れた。
「くそーっ」
悔しいがどうにもならない。相手の方が二回り大きく、強そうだった。僕はこの種の格闘には自信が無い。殴り合いのケンカをしたのは小学校五年の時が最後だった。あの時は、姉と組み合ってケンカしていたら、姉が机の角に自分の手をぶつけて血を出した。父にこっぴどく叱られて、今後一切人に暴力を振るわないと約束させられた。先に手を出したのは姉の方だったし、姉は僕を殴ろうとした手を振り上げた時に勝手に机の角にぶつけたのに……。でも、僕は反論せずに謝ったので、後で姉が急に優しくなり、それ以来姉とは大の仲良しだ。
地面に手をついて若い男の顔を見上げた時、恐ろしい光景が目に入った。僕が股間を蹴り上げた店長が、ゆっくりと僕の方に歩いて来る姿だった。
――殺される……。
若い男は僕の髪の毛を手でつかんで立たせ、背後に回って僕の両肘に腕を絡ませた。僕は身動きが取れない状態で、大男の店長と向き合う形になった。
「大事なものを潰されると困るんだよな」
と店長は言って、右手を僕の股間に差し込み、僕のモノをギュッと掴んだ。
「ギャー、許して! ゴメンナサイ!」
言葉に言い表せない痛みに襲われて、僕は叫んだ。
「お客さん、自分がしたことには責任を取ってもらうよ。二つの玉とはお別れと思った方がいいな」
「それだけは許して! もう二度としませんから勘弁してください」
「お客さんなら、玉を取ってしまえば、いい働き口を世話してあげられるよ。九万六千円と、俺の玉が潰れそうになった見舞い金も働いて返してもらわないとな」
「それって、まさか……」
「そういうことさ。お客さんの場合は玉が無くなった方が楽な人生が送れるんじゃないの?」
「ご冗談を!」
「さあ、来るんだ!」
絶体絶命だった。
「助けてえ!」
と大声で叫ぼうと息を吸った瞬間、若い男に口を押さえられた。
店長が僕の大事なものをグッと握りなおしたので、僕は痛みのあまり気が遠くなりそうだった。
「潰さないで、お願い……」
頭から抜けるような高い声で懇願したが、力が入らなかった。
「いててててててっ!」
突然、店長が声を上げて、僕の股間から手を離した。
「何するんだっ!」
「穏やかじゃないですね。嫌がってますよ」
店長と同じぐらい大柄な五十絡みの男性が、店長の手首を掴んでいた。いい身なりをした紳士だった。
「こいつが代金を払わずに逃げようとしたんだ。俺の股間を蹴り上げて逃げたから、どんなに痛かったかを教えてやっているだけさ」
「代金はいくらだったんですか?」
「二十五万円だ」
紳士は背広のポケットから大きな厚い財布を取り出し、店長に札束を手渡した。
「これで手を打ってもらおう」
店長は札束を数えた。
「五十万か、まあいいだろう。おい、ゲン、行くぞ」
ゲンと呼ばれた若い客引きは僕の肩を掴んでいた手を離した。
店長とゲンが立ち去り、僕は絶体絶命の危機から解放された。
「あなたは僕の命の恩人です。本当にありがとうございました」
「ぼったくりバーに引っかかったんだね」
「四千円ぽっきりと言われて入ったら、二十五万円も請求されました。現金とクレジットカードの枠で十五万四千円払ったから、残りは九万六千円なんですよ。五十万も渡すことなかったのに……」
「金額の問題じゃない。こういう場合は後腐れが無いようにするのが大事だ」
「買ったばかりのスマホを取り上げられて、キャッシュカードで九万六千円を引き出したらスマホを返すと言われました。一緒に店を出たところで、僕をだました客引きを見つけて頭に来たんです。アッ、どうしよう! まだ財布もスマホを返してもらっていませんでした。一緒に店まで行っていただけませんか?」
「スマホなんて金を出せば買えるし、ちゃんとしたメーカーのスマホならメーカーからロックを掛けたり初期化してデータを消すこともできる。カード類は紛失届を出せばいい」
「でも、スマホが無いと、僕、何もできません。現金は全部取られたし、クレジットカードも限度額一杯使われてしまったし、キャッシュカードもアパートのカードキーも財布の中です。やっぱり店に行って返してもらわないと……」
「銀行口座の残高は?」
「六万円ちょいです。もうすぐ会社から給料と退職金の合計で二十数万円入金する予定ですけど」
「退職金? 会社を辞めたのか?」
「今日退職届を出したんです」
「それで四千円ぽっきりで憂さ晴らしをしようとして身ぐるみ剥がれ、玉まで取られそうになったというわけか、アハハハ」
「笑い事じゃないですよ。僕の身にもなってください。一文無しでアパートにも帰れないんですよ!」
「五体満足で何よりだったじゃないか。この辺には二度と近寄らないようにするんだよ。ああいう人種の股間を蹴り上げておいて、タダで済むと思ったら大間違いだ。私がいない場所でキミを見つけたら、飛んで火にいる夏の虫とばかりに仕返しをするだろう。その時には玉がついたまま家に帰るのは無理だと思った方がいい。キミの場合は玉を潰されるだけでは済まないかもしれないよ」
「そう言えば、玉を取って働き口を世話するみたいなことを言われました」
「あいつらがキミを見たら当然思いつくことだ」
「どうしましょう。カード情報を取られたし、スマホを見ればアパートや実家の住所も交友関係もすぐにわかります」
「スマホは暗証番号なしで開けるのか?」
「クレジットカードの暗証番号と同じなので、もうあの店長にスマホの中を見られました」
「当分アパートには帰らないことだな」
「僕はどうしたらいいんでしょうか……」
「ほとぼりが冷めるまで私の家に泊まればいい」
「本当ですか!」
「困ったときはお互い様だ」
「あなたは本当に僕の命の恩人です! まるで、白馬に乗って現れた王子様みたいです!」
「おいおい、白馬の王子様とは女性が若いイケメン男性を指して言う言葉だぞ。それを言うなら白馬の騎士、ホワイト・ナイトと言うべきだろう、アハハハ」
紳士は大通りに出てタクシーを拾った。タクシーが紳士の自宅に着いたのは午後十一時過ぎだった。
***
それはタイル壁に鉄格子の門のある邸宅だった。西郷竜太郎という表札を見て、紳士の名前を知った。玄関のドアを鍵で開けて入ると玄関ホールの灯りがついた。
「ユキコ、ただいま」
西郷が言ったが返事はなかった。
「突然こんな時間に他人を連れて帰ったら奥さまに叱られません?」
「ユキコは、決して私に腹を立てることはない」
「でも、僕がしばらく居候すると知ったら、さすがの奥さまもお怒りになるのでは……」
「ユキコは去年の暮れに旅に出たんだ」
「長いご旅行ですね。海外ですか?」
西郷は目を閉じ、数秒後に憂いを湛えた口調で言った。
「天国へと旅立ったんだ」
僕には返すべき言葉が見つからなかった。
「キミのように元気で屈託のない人が居れば心が晴れる。気兼ねせずにゆっくりしてくれ」
玄関ホールの右側の扉を開けると、そこは広いリビングルームだった。西郷は背広を脱いでハンガーに掛けた。
「家内が死んでしばらくは帰宅して背広を脱ぐと床に置いたままにしていた。ハンガーに掛けるだけの心の余裕が出てきたのはつい最近の事だ。この家のごく一部分を使ってひっそりと暮らす毎日なんだよ……」
「広そうなおうちですね。全部で何部屋あるんですか?」
「一階はリビングルーム、キッチン、応接室、客間、浴室と納戸、二階には夫婦の寝室、私の書斎、家内の部屋、クローゼット、浴室がある。三階はアティックで、地下には物置があるが何年も使ったことが無い。トイレは各階にある」
「すごい豪邸ですね! うらやましい!」
「何がうらやましいものか。ごく一部だけを使って暮らしているが、家内が死んでから一度も掃除していない部屋が殆どだ」
「じゃあ、泊めていただくお礼に僕が掃除します」
「それは助かる。さあ、今夜は風呂に入ってゆっくりとくつろぎなさい。私は二階の浴室を使うから、キミは一階で風呂に入ればいい」
西郷はキッチンから廊下を隔てた側にある一角に僕を案内した。一人暮らしには大きすぎるドラム式の全自動洗濯機、広々とした洗面所、浴室とトイレのドアがある空間だった。
「着替えを出しておいてあげるから、洗濯物はその洗濯機の中に入れておきなさい」
と言って西郷は立ち去った。
背広とズボンを脱いで脱衣かごに入れた。背広には泥がついており、ズボンのお尻が擦り切れていた。若い男に路上に転がされた時のものだろう。カッターシャツと下着のシャツ、パンツと靴下は西郷に言われた通り洗濯機に入れた。
浴室は二、三人が一緒に入れるほど広く、洋式の浴槽は大柄な西郷でもゆったりと寝られそうなほど長い。僕なら入浴中に居眠りしたら溺れてしまいそうだった。膝とお尻に擦り傷ができてヒリヒリしていたし、店長につかまれた玉が、まだ腫れている感じで痛かった。血管が切れたり捻じれたりして、玉がダメになっていないかと心配になった。
普段より時間をかけてシャンプーとリンスをして湯船に浸かると、緊張が解けてきた。
波瀾の一日だった。退職届を出し、初めて一人でバーに行き、ぼったくられ、逃げて捕まえられて、玉を潰されそうになったところを西郷に助けられた。一歩間違えれば男に身体を売る身分にまで転落していたかもしれなかった。
タオルを絞って身体を拭き、風呂を出ると脱衣かごに入れた背広とズボンはどこかに片付けられ、代わりにパジャマとパンツが置いてあった。女物だった。亡くなった奥さんのものなのだろう。
女物のパンツをはくことには抵抗があったが、立場上文句は言えない。西郷がトランクス派かブリーフ派かは知らないが、いずれにしても僕には大きすぎて着心地が悪いに決まっている。長袖のパジャマはちぢみの白地に赤い水玉模様で、ズボンはすね丈だった。普段とは左右が逆のボタンを左手で掛けるのに手間取った。
洗面所の鏡で見ると、まるで女性のように見えた。
リビングルームに行くと、西郷はソファーに座ってビールを飲んでいた。西郷は僕が入って来る姿を鑑賞するように見た。
「やはりサイズはちょうどいいようだな」
女物を出したことについて西郷が「私のでは大き過ぎるから」と説明するだろうと予想していたが、西郷がそのことに触れなかったので僕はほっとした。女物を着るのは初めてだとか、着心地が微妙に違うとか、僕の方から言い訳をする羽目にならなくて済んだ。
「キミも飲みなさい」
ソファーの前のガラステーブルには僕の分のグラスも置いてあって、西郷がビールを注いで渡してくれた。僕はグラスを上げて
「今日は本当にありがとうございました」
と改めて礼を言ってから口をつけた。
「そういえばまだ名前を聞いていなかったな」
「あ、失礼いたしました。保科流宇と申します。るうは流れるに宇宙の宇と書きます」
「流宇という名前の人に会うのは初めてだ。いい名前だね! キミにピタリだ」
「ありがとうございます!」
「しかし、どう考えても女性の名前だが……」
「とんでもない! ルウはルイスやルーカスの略称で、アメリカ人が聞いたら誰でも男性だと分かる名前だと教えられました」
「それは知っているよ。私のビジネス・フレンドにもルウ・ジョンストンという人がいる。でも漢字で流宇と書けばまず女性だ。他の人からも言われたことがあるだろう」
「まあ、時々間違えられます。大学の夏休みにバイトに行ったら、名簿を見て女子の仕事を割り当てられていて、女子の制服を渡されて焦ったことがありました」
「それで、キミは女子の制服を着て働いたのかね?」
「まさか! バイト先の人から冗談半分でそう言われたんですけど、絶対にイヤだと断って、私服のまま働きました。仕事の割り当ては女子のままでしたから、僕以外は全員女子の六人のグループで一ヶ月ほど仕事が出来て、最高の思い出になりました」
「人の一生は名前に左右されると言われるがその通りかもしれないな。西郷竜太郎として生まれ育った私は、身体もデカいし、性別が揺らぐような経験は一切したことがない。キミは今日もニューハーフヘルスとかに売り飛ばされる寸前だったじゃないか。あの男たちがカードやスマホに表示された流宇という名前を見なければ、そんな過激なアイデアを思い付かなかったかもしれない。勿論、キミの顔や体格による部分も大きかったのだろうが」
「男らしい名前に改名した方がいいですかね? 流之介とか……」
「それはやめた方がいい。流宇として生まれ育って、流宇といういい感じの人物像が出来上がっている。そのままにしておくことだ。さあ、明日からは会社に行かなくていいんだから、グッと飲んでリラックスしなさい」
西郷は話し上手で、聞き上手、そして飲ませ上手だった。僕は家族のことから好きな女優に到るまで聞かれるままに話した。まるで合コンのような雰囲気だった。
僕はつい自分の限度以上に飲み、気持ちよくなってうとうとしているうちに眠ってしまった。
続きを読みたい方はこちらをクリック!